

2001年東北大学大学院工学研究科機械電子工学専攻博士後期課程修了。(独)理化学研究所、東北学院大学工学部講師、東北学院大学工学部准教授(2013年9月~2014年8月ケンブリッジ大学工学部在外研究員)を経て2019年より東北学院大学工学部機械知能工学科教授。
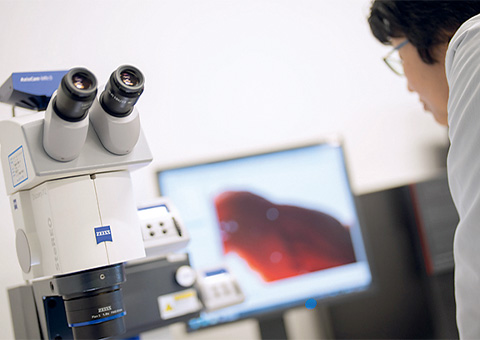
生体工学研究室が取り組むのは、血液循環に関するバイオメカニクス、新規材料の開発、細胞運動解析手法の構築という3つのテーマ。加藤教授が特に注力しているのは、循環器系疾患や胎盤の血液循環メカニズム、マボヤ被嚢(マボヤという生物の外皮)組織の力学的特性評価、そして細胞運動解析である。
「自覚症状に乏しい血液循環系の疾患にとって、進行の把握は重要になります。だからこそ、そのメカニズムを明確にして、診断支援に役立てたいと強く考えています」。
胎盤では、villous treeの収縮がもたらす力学的環境の変化と血流との関連性を解析し、検証結果を確認した。同様に胎盤や臍帯における力学的環境に関する有限要素モデル構築と解析を行ったが、これらの結果は、血流に直接的に影響する力学的環境についての数値解析モデルの構築と実施結果に相当する。
また、マボヤ被嚢の能動変形特性を解明し、新素材としての応用を模索。今後は、この被嚢組織が力学的刺激や神経伝達物質に反応して変形する特性を活かし、実際に人工的につくることを想定した数値解析モデルの構築と、適用について取り組む予定だ。
細胞運動解析では、明視野における細胞運動の観察結果を定量的に評価する手法を確立した。これにより、細胞の形などから受ける力の特性を視覚的に示す研究が進行中である。これらの研究は、医療分野や材料工学の未来を切り拓く可能性を秘めている。
「研究に取り組んで、その結果を論文で発表することだけで幸せを感じます。その過程には困難も多くありますが、それを上回る楽しさがあります」。
この研究の楽しさを、学生にも味わってほしい。
「八方ふさがりに見える状況下でも冷静に、根気よく、柔軟に、解答を模索できることが成功のカギとなります。ピンチはチャンス、チャンスはピンチ。健闘を祈ります」。
今後は、循環器系疾患や胎児発育に関する診断支援技術の実用化を見据えつつ、マボヤ被嚢を活用した新素材の実現を見据える。また細胞運動解析技術を進化させ、力学特性を可視化することで、研究成果を社会に還元する計画だ。
その歩みは、医学と工学の未来を切り拓く一歩となるだろう。