アジア流域文化研究所「日中韓周縁域における信仰のありかた」公開講演会開催報告
2016年12月14日
東北学院大学アジア流域文化研究所公開講演会「日中韓周縁域における信仰のありかた」が、11月26日、土樋キャンパスホーイ記念館多目的ホールにて行われました。
講演会開始に先立ち、所長の歴史学科谷口満教授は「一連のプロジェクトも14年が経ち、今年度が最終年であり、本日の講演会が最後の公開行事となります。長い間お付き合いいただきありがとうございました」とあいさつしました。
第一部では「中国重慶地区の移民とその信仰」と題し、重慶師範大学歴史与社会学院の李禹階教授が登壇。湖南や湖北などの省からたくさんの人々が重慶に移民したことで、人口や経済へ大きな影響を与えたと説明。信仰においても元から存在していた土着信仰と移民たちが持ち込んだ移民信仰が混在したが、先住民も移民もそれぞれの信仰を信じながら、ともに神をまつり、ともに寺を建てたと指摘しました。
 |
 |
||
 |
 |
 第二部では「韓国の宗教構造と民間信仰 ─民衆の信仰から民族の文化へ」と題し、神戸大学大学院国際文化学研究科の岡田浩樹教授が登壇。韓国ではシャーマンが人間文化財に指定されるなど民族宗教が国民文化に選ばれたり、宗教や信仰などを押さえつける政権に対するアンチテーゼとなったりしていること、また、民間信仰というのは永遠に変わらないものではないこと、人々が身のまわりの世界を説明する手段として用いられていること、民間信仰を見ていくと社会や人々が抱えている問題が見えてくることなどを解説しました。
第二部では「韓国の宗教構造と民間信仰 ─民衆の信仰から民族の文化へ」と題し、神戸大学大学院国際文化学研究科の岡田浩樹教授が登壇。韓国ではシャーマンが人間文化財に指定されるなど民族宗教が国民文化に選ばれたり、宗教や信仰などを押さえつける政権に対するアンチテーゼとなったりしていること、また、民間信仰というのは永遠に変わらないものではないこと、人々が身のまわりの世界を説明する手段として用いられていること、民間信仰を見ていくと社会や人々が抱えている問題が見えてくることなどを解説しました。
続く第3部では「アイヌ葬送儀礼の復活」と題し、フリーランス記者の平田剛士氏が登壇。アイヌの人々の遺骨が全国12の大学に収集されていたが、北海道大学からアイヌの人々へようやく遺骨が返還されたこと(4体は未返還)、その遺骨返還を機に、先人たちの魂を鎮めるアイヌ葬送儀礼である、神々に祈りを捧げる「カムイノミ」が7月15日〜17日に北海道浦河町にて復活再現されたことなどを説明しました。
そして、アイヌの血を引き、民族衣装をまとったコタンの会副会長の葛野次雄氏とアイヌ宗教儀礼伝承者で札幌大学学生の葛野大喜氏(次雄氏のご子息)が登壇。近代以来の苦難の歴史を克服して、アイヌ本来の暮らしを取り戻していきたいと力強く語りました。
その後は会場の外で「カムイノミ」を実演。李禹階教授・岡田浩樹教授をはじめとする関係者の方々も参加し、ともに神々へ感謝する伝統儀式を体験しました。
また、翌27日には牡鹿半島小渕浜にて葛野次雄氏と葛野大喜氏に加え、東北学院大学災害ボランティアステーションが協力しあい、「東日本大震災被災者慰霊のカムイノミ」を執り行いました。
14年に及ぶプロジェクトのなかで、アジア流域における多種多様な文化をお伝えしてきましたが、最後の公開講演会も無事に閉会することができました。これまでご参加いただきました多くの皆様に深く感謝申し上げます。
 |
 |
||
 |
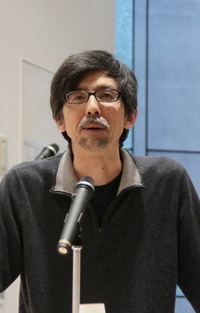 |
 |
 |
|
