大学間連携災害ボランティアネットワーク主催シンポジウム 「東日本大震災と学生ボランティアの役割―大学間連携による取り組みとその課題―」 開催 レポート-②
2011年12月28日
【セッション2】
12 月 17 日(土)は 9 : 00 から、大学間連携による『夏ボラ』参加大学の学生による報告が行われました。
関西学院大学、桜美林大学、麗澤大学、西南学院大学、名古屋学院大学、明治学院大学、東北学院大学が順番に発表。気仙沼・唐桑に入っての 11週にもおよぶボランティア活動の多岐にわたる活動内容が報告されました。
 桜美林大学 |
 関西学院大学 |
 麗澤大学 |
 西南学院大学 |
 名古屋学院大学 |
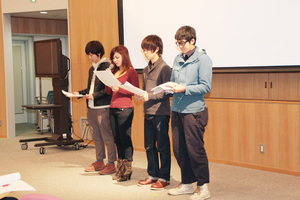 明治学院大学 |
 東北学院大学 |
 「夏ボラ」の総括を報告する東北学院大学災害ボランティアステーション学生代表、菊地崇史さん |
続いて、11:00 からは気仙沼の現状を被災者である気仙沼の方たちの生の声を聞く「気仙沼の現況と展望」というラウンドテーブルがスタート。気仙沼市から、東北学院同窓会気仙沼支部長・齋藤商店社長の齋藤欣也氏、同事務局長の庄司幸男氏、同じく同窓生であり、気仙沼市議会議員の守屋守武氏(階上地区ボランティアセンター責任 者)の三氏を招き、本学教養学部の山崎冬太先生と経済学部の郭基煥先生のコーディネートによるラウンドテーブルです。


気仙沼市から駆けつけた 3 名の報告者
齋藤氏、庄司氏からは、震災直後の生々しい被災地の様子や復旧に向けての苦労談などを報告いただき、実際に津波被害を受けた 階上地区でボランティアセンターを運営する守屋氏からは、被災者とボランティア側との意識の違いなどを指摘する発言もあり多くの教訓が含まれたラウンドテーブルでした。
昼休みをはさんで午後からはいよいよ最後のセッション 3 です。
13:30 から山形大学の平尾清先生、神戸学院大学学生、宮城学院大学学生、熊本学園大学学生による「震災ボランティアへの取り組みとその課題」のパート 2 が開催され、それぞれの大学で実施した被災地支援活動のレポートが行われました。
 山形大学エンロールメント・マネジメント部 平尾清先生 |
 ボランティアバスを報告する神戸学院大学 学生 |
 立命館大学教学部 共通教育課 サービスラーニングセンター 冨田沙樹氏 |
 宮城学院女子大学 学生 |
 熊本学園大学 学生 |
そして 2 日間にわたるシンポジウムの最後に、すべてのセッションに参加いただいた似田貝香門先生に総評をいただきました。
「全国の参加学生が、東北学院大学のコーディネートによってさまざまなボランティア活動が実行された。これから何年も続くであろう被災地支援の活動で、この後 10 年後、 20 年後共に活動した仲間が全国に広がっていることを認識することは大きな意義がある。そのことに気づきこうして発表できる学生諸君の意識の高さを評価する」と語りました。
閉会のあいさつでは佐々木俊三東北学院大学災害ボランティアステーション所長が、今後の取り組み方の多様性を示唆しつつ、「こうした発表の場が遅くなったことをお詫びする」と語り、「次はいつ集まろうか ? 」と、ユーモアを含めて締めくくりました。

最後の挨拶を述べる
佐々木俊三 東北学院大学災害ボランティアステーション所長
