【敬神愛人】「ご存知ですか?労働会の文芸活動」(史資料センターWEBコラム)
2025年07月22日
明治期の東北学院に存在した「労働会」は、学費に困窮する学生たちが働きながら学ぶことを目的に、1892(明治25)年に創設された学生団体です。寄宿舎での共同生活を基盤に、新聞配達や牛乳販売、印刷業などの活動を通じて自給・自立を目指しました。その一方で、「文武を兼備し、理想と実行とを伴はしめんと欲す」という労働会の理念のもと、学問や労働のみならず文芸活動に励んでいたことは、あまり知られていないかもしれません。その一端を示すものとして、学生たちが自ら執筆・編集した機関誌の存在が挙げられます。
労働会機関誌は1893(明治26)年11月から1898(同31)年9月に第25号で終刊を迎えるまでの数年間発行されています。最初は、編集者3名による手書きの雑誌『松籟(しょうらい)』が1893(明治26)年11月に創刊されました。『松籟(しょうらい)』とは松の梢に吹く風の音を意味します。この雑誌では、宗教雑感、時事批評、雑録等が掲載されていました。毎月発行され、その十数号に及ぶ『松籟』は労働会塾舎の南六軒町移転に際し休刊します。その後、『松籟』の記者たちは再発行を試みますが、同じ労働会機関誌に『労働会文学』が存在したため、再発行には至りませんでした。
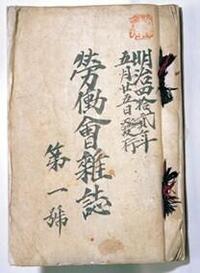
図1:労働会雑誌 |
1895(明治28)年、これら2誌を統合した『労働会雑誌』および『附録文集』が刊行されます。しかし、創刊後まもなく『芙蓉峰(ふようほう)』へと再改題されました。その背景には、既存の誌名では当時の出版法による取締り対象となる恐れがあったことが理由のひとつと考えられます。誌名には、富士山の異称「芙蓉峰」に寄せた愛着がにじみます。1896(明治29)年に発行された『芙蓉峰』第1号の目次を見てみると、「芙蓉の雪(論説)」「寒梅の林(雑録)」「シオンの月(押川先生談話)」「幽谷の花(先哲格言)」など、多彩な構成であったことが分かります。なかでも「シオンの月」には、東北学院創設者・押川方義に対する敬意と信頼が感じられ、記者たちや労働会の精神的支柱となっていたことが伝わってきます。
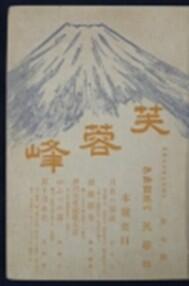
図2:『芙蓉峰』 |
『芙蓉峰』は、記者の多忙と購読料の未納による財政的な困難から1898(明治31)年9月に第25号で終刊を迎えると、以降、労働会機関誌の発刊も行われなくなりました。それでも、学生たちが取り組んだ文芸活動は注目に値します。これらの機関誌は学生の手によって書かれたものであり、そこには当時の若者が何を理想とし、どのように生きようとしたのか、その価値観や知的関心が色濃く表れています。労働会の文芸活動は、東北学院の学生の興味関心を今に伝える、貴重な歴史資料だといえるでしょう。
